特別法と強行規定
特別法と強行規定
利息制限法、完全解説サイト>利息制限法とは>特別法と強行規定基礎知識として利息制限法と民法の関係を
特別法と強行規定という面から解説したいと思います。
スポンサードリンク
「利息制限法は特別法で第1条は強行規定です」
と、言われて意味がわからないと思いますので、
基礎知識として解説していきます。
法律には幅広く色んなことについて
規定している一般法と、
一般法の内容を修正したり内容を付け加える形で存在する特別法というものがあります。
幅広く規定している一般法は「民法」だけです。
なので基本的には民法の内容に従っておおむね世の中のルールは成り立っていますが、
民法の条文を修正する形で特別法というものが局所的に存在します。
具体例として利息です。
民法で法定利率(法律で定めた利率)は以下のようになっています。
(法定利率)
第四百四条
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
民法では404条に
「利息は年利5%にしてください」
という条文があります。
しかし、特別法にあたる商法、利息制限法、出資法には以下のような条文があります。
商法
(商事法定利率)
第五百十四条
商行為によって生じた債務に関しては、
法定利率は、年六分とする。
商法514条では
「商行為の場合年利6%にしてください」
と定めている。
商行為とは
おおむね「利益を得るための活動」
と思って下さい。
スポンサードリンク
利息制限法
(利息の制限)
第一条
金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、下記に従って超過部分を無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
利息制限法1条では
「お金の貸し借りの時はおおむね年利20%が上限」
と定めている。
出資法
(高金利の処罰)
第五条
仕事として金銭の貸付けを行う者は、年20%を超える利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金とする。
出資法5条では
「20%を超える年利で貸したものは罰則があります」
と定めています。
ここでまとめると、
・民法→年利5%
・商法→商行為時、年利6%
・利息制限法→金銭貸付の場合、年利20%まで
・出資法→金銭貸付の場合、年利20%超えると罰則あり。
という感じになります。
一般法である民法は年利5%と定めていますが、
商行為をした時のみ、特別法である商法によって
年利6%が優先的に適用されます。
さらに金銭を貸し付ける仕事の場合のみ、
特別法である利息制限法と出資法によって年利20%までという規制がかかります。
このように特定条件の時に一般法の内容を修正、
あるいは特定条件の時に一般法の内容にルールを付け加える、
といったことが特別法になってきます。
ここまでが一般法と特別法の説明です。
さらに法律の条文には任意規定と強行規定というものがあります。
任意規定
当事者の契約の不備で予期できないことに出くわしたときに
その処理をどうするかを規定した条文。
強行規定
契約をしてもこの条文に違反している場合は、この条文に従わせるもの。
例えば、
民法の法定利率は「別段の定めがないときは5%」と書かれています。
別に当事者で利率を定めた場合はこの法定利率5%は関係ないということです。
これは任意規定にあたります。
一方、法律の内容に従わせる強行規定はというと、
利息制限法1条の「年利20%を超えると無効だよ」という条文です。
これは当事者の契約内容に関係なく、20%を超えるかどうかで超過部分が無効であるかどうかを
強制的にジャッジしているので強行規定となります。
最後に最初に書いた言葉を書いてみます。
「利息制限法は特別法で第1条は強行規定です」
意味が理解できたでしょうか?
スポンサードリンク
その他、基本的なことを確認するなら、
「利息制限法とは」
のページに戻って参照して下さい。
バナースペース
よく閲覧されているページ

過払い金について
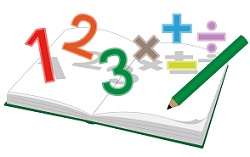
利息の計算方法
合わせて確認しておきたい関連サイト
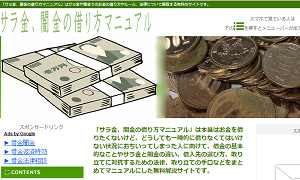
サラ金、闇金の借り方マニュアル
何かございましたら
menhpkanri@yahoo.co.jp
までご連絡下さい。